「ド」から次の高さの「ド」まで音を順番にならべていくと、 「ドレミファソラシド」となりますね。 これが音の階段、つまり音階になります。 英語ではScale(スケール)といいます。
音階の音にはそれぞれに名前がついています。 名前とともに音それぞれには役割があります。
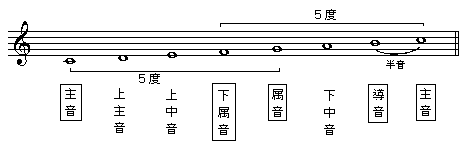
音階は種類によって音の並び方に決まりがあります。 長音階は「ミとファ」、「シとド」が半音になっています。 「ドレミファソラシド」は長音階なんですね。 明るい響きが特徴です。
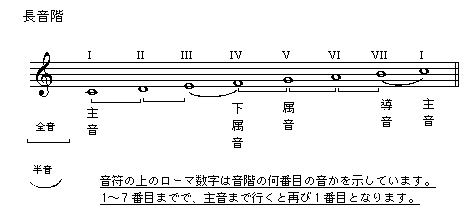
短音階は3つに分かれます。 それぞれ並び方が違うので注意しましょう。
短音階の原形です。7番目と主音が半音になっていないため この音階には導音がありません。 明るい響きの長音階に比べると、暗い感じのする音階です。
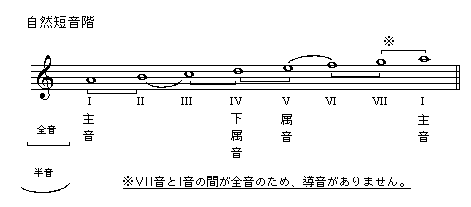
自然短音階には導音がありませんでした。 導音がないと、曲が終わった感じがしません。 そこで、7番目の音を半音上げて導音を作ってしまった音階が 和声短音階です。「6番目と7番目」の音の間隔が「全音+半音」 になったため、少し独特の響きになっています。
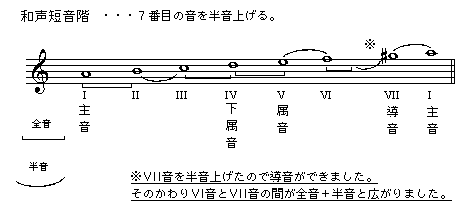
和声短音階によってできた導音により、6番目と7番目の間が広がりました。 この広がりをなくし、なめらかな音階にしたものが、旋律短音階です。 まず、上にむかって6、7番目を半音上げます。 下りは6、7番目をもとの音の高さに戻します。 これは導音は特に主音に向かって上がる時にその効力を発揮するので 下がる時はあまり必要がないからです。 旋律短音階は上行、下行と並び方が違うので注意しましょう。
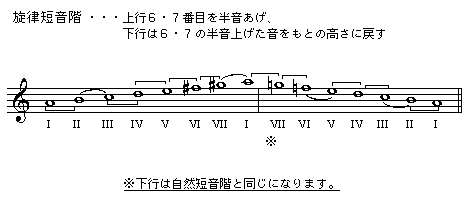
|